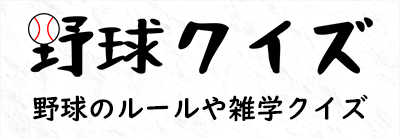「とりあえず、送りバント」は正解なのか?第1回

夏の甲子園、高校野球選手権大会の通算本塁打記録が準々決勝の時点で更新されました。
南北海道大会を振り返っても「今年はやけにホームランが多いなあ」と感じることが多かったですし、今大会でもホームランを含め大量得点が入るケースが多く、3・4点のアドバンテージで精神的な余裕が生まれないような、そんな試合展開が何試合もありました。
一方で、試合の中で「送りバント」という作戦を選択することがたくさんあります。
両チームの投手の調子がよく、なかなか点数を上げられない試合というのも一方であるわけです。
そういった試合展開を両チームの監督が予想されると、送りバントという作戦を序盤、接戦の中盤、決めの終盤と、とにかく「1点以上」の得点を得るときに用いられることが多いと思いますが、果たして戦略的に送りバントを講じることは1得点をあげやすいのか?を考えてみたいと思います。
ちなみに、2011年に東京学芸大学の准教授であった及川氏や現在ファイターズの監督である栗山氏がプロ野球の公式戦で行われたプレーを元に膨大なデーターをとり考察されております。
プロ野球のデーターを元にした考察に関してはこちらをご覧になって下さい。
■送りバントとは?
0アウト、1アウトで、1塁もしくは2塁の塁上にランナーがいるケースで、打者はバットをスイングせず、意図的にボールを当てて打球を緩く転がし、塁上にいるランナーを先の塁に進塁させる作戦のこと。
走者を進塁させることが目的なので、記録上は「犠打」が記入される。
ノーアウト1塁から、送りバントによってワンアウト2塁のケースから、少なくとも1点をとれるパターンは、次打者の安打が2塁打以上であれば1点は間違えなく入りますが、次打者の結果が
・単安打
・失策
・野手選択
であれば、条件が付くことになります。
単安打での得点であれば、打者がボールを打った時点での走者のスタートや守備側の守備位置、守備者の能力によって得点出来たり、出来なかったりが発生します。
失策であれば、野手が失策をしたあと打球がどこに転がるかや、失策後の野手の判断力が問題になりますし、野手選択での出塁も同様のことが言えると思います。
ランナーが2塁に進むことを「得点圏にランナーが進んだ」と表現しますが、ワンアウトランナー2塁のケースからどうするか?というところが得点に「なるか、ならないか」で以降の展開が監督の手腕の見せ所といえると思います。
※ちなみに、ノーアウトランナー1塁の後に「犠打」と「安打」が必ず成功するという計算の元だと、
ノーアウトランナー1塁→ワンアウトランナー2塁→ワンアウト一・三塁
ノーアウトランナー1塁の後に「安打」と「犠打」が必ず成功するという計算の元だと、
ノーアウトランナー1塁→ノーアウトランナー1塁・2塁→ワンアウト2塁・3塁
と、作戦の順番を変えるとランナーの置き方も変わるというところももう一方でありますね。
また、絶対に送りバントをするということが守備側にわかっている場合、守備力に自信のあるチームは送りバントを完成させないような守備隊形をとる傾向が近年見受けられることが多くなりました。
確実に決めてほしいノーアウトランナー1塁なのに「送りバント」でランナーを進塁させられないどころかダブルプレーでツーアウトランナー無しという結果をしばしば目にします。
「送りバント」はできて当然と思われがちな作戦なので、失敗すると失敗した打者を責めるコメントも聞こえてきますが、投げる投手は打たれようと思って「バントのしやすいボール」を投じるわけではありませんし、また守る側も「転がるボールを捕球する」つもりで守りますから「投手が失敗させようと思って投じているボールを野手がとりにくいところに転がす」というのは結構難しいことではないでしょうか?
こうなってしまうと「送りバント」という作戦は「無難」ではなく、「リスクの高い」作戦と思ってしまします。(つづく)
この記事について問合せをする
南北海道大会を振り返っても「今年はやけにホームランが多いなあ」と感じることが多かったですし、今大会でもホームランを含め大量得点が入るケースが多く、3・4点のアドバンテージで精神的な余裕が生まれないような、そんな試合展開が何試合もありました。
一方で、試合の中で「送りバント」という作戦を選択することがたくさんあります。
両チームの投手の調子がよく、なかなか点数を上げられない試合というのも一方であるわけです。
そういった試合展開を両チームの監督が予想されると、送りバントという作戦を序盤、接戦の中盤、決めの終盤と、とにかく「1点以上」の得点を得るときに用いられることが多いと思いますが、果たして戦略的に送りバントを講じることは1得点をあげやすいのか?を考えてみたいと思います。
ちなみに、2011年に東京学芸大学の准教授であった及川氏や現在ファイターズの監督である栗山氏がプロ野球の公式戦で行われたプレーを元に膨大なデーターをとり考察されております。
プロ野球のデーターを元にした考察に関してはこちらをご覧になって下さい。
■送りバントとは?
0アウト、1アウトで、1塁もしくは2塁の塁上にランナーがいるケースで、打者はバットをスイングせず、意図的にボールを当てて打球を緩く転がし、塁上にいるランナーを先の塁に進塁させる作戦のこと。
走者を進塁させることが目的なので、記録上は「犠打」が記入される。
ノーアウト1塁から、送りバントによってワンアウト2塁のケースから、少なくとも1点をとれるパターンは、次打者の安打が2塁打以上であれば1点は間違えなく入りますが、次打者の結果が
・単安打
・失策
・野手選択
であれば、条件が付くことになります。
単安打での得点であれば、打者がボールを打った時点での走者のスタートや守備側の守備位置、守備者の能力によって得点出来たり、出来なかったりが発生します。
失策であれば、野手が失策をしたあと打球がどこに転がるかや、失策後の野手の判断力が問題になりますし、野手選択での出塁も同様のことが言えると思います。
ランナーが2塁に進むことを「得点圏にランナーが進んだ」と表現しますが、ワンアウトランナー2塁のケースからどうするか?というところが得点に「なるか、ならないか」で以降の展開が監督の手腕の見せ所といえると思います。
※ちなみに、ノーアウトランナー1塁の後に「犠打」と「安打」が必ず成功するという計算の元だと、
ノーアウトランナー1塁→ワンアウトランナー2塁→ワンアウト一・三塁
ノーアウトランナー1塁の後に「安打」と「犠打」が必ず成功するという計算の元だと、
ノーアウトランナー1塁→ノーアウトランナー1塁・2塁→ワンアウト2塁・3塁
と、作戦の順番を変えるとランナーの置き方も変わるというところももう一方でありますね。
また、絶対に送りバントをするということが守備側にわかっている場合、守備力に自信のあるチームは送りバントを完成させないような守備隊形をとる傾向が近年見受けられることが多くなりました。
確実に決めてほしいノーアウトランナー1塁なのに「送りバント」でランナーを進塁させられないどころかダブルプレーでツーアウトランナー無しという結果をしばしば目にします。
「送りバント」はできて当然と思われがちな作戦なので、失敗すると失敗した打者を責めるコメントも聞こえてきますが、投げる投手は打たれようと思って「バントのしやすいボール」を投じるわけではありませんし、また守る側も「転がるボールを捕球する」つもりで守りますから「投手が失敗させようと思って投じているボールを野手がとりにくいところに転がす」というのは結構難しいことではないでしょうか?
こうなってしまうと「送りバント」という作戦は「無難」ではなく、「リスクの高い」作戦と思ってしまします。(つづく)

とりあえず「送りバント」は正解なのか?3回目

ノーアウト満塁で攻撃側が点数を上げられるパターンは1・3塁や2・3塁より少ない
ノーアウト満塁はなぜ点数が入らないのか?

結論:結局のところ自分に合うかどうかは自分にしかわからないんです
良いグラブ(グローブ)とは何か?
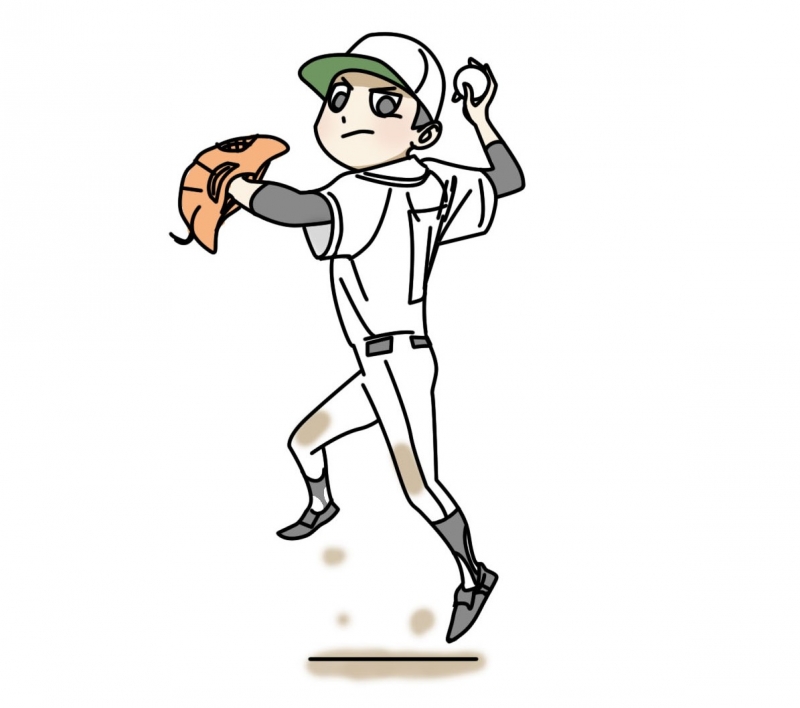
グラブ・スキル以前にすべきこと。状況によって求められるスキルは違う「高いレベルの感覚」と小学校・中学校でのベストプレーは実は同じではない
野球の「捕ってから早く投げる」という事について

上手な選手は普段の練習から「取り組み方」が違う
野球の守備が上手な選手は何が違うのか?

とりあえず「送りバント」は正解なのか?3回目

とりあえず「送りバント」は正解なのか?第2回

グラブ平裏部分直刺繍(MIZUNOPROロゴ) 。フィット感UP+グラブの握り込みをサポートしてくれる5Dベロを使用
【ミズノプロ】硬式野球用グラブ/グローブ(菅野智之投手モデル・投手用・1AJGH97801)

ゼットプロステータス今宮モデルグラブが出来るまで
今宮健太選手がグラブにもとめるこだわり

10歳〜14歳のゴールデンエイジ期間の選手向け。ぐぐんと野球が上手くなる時期、手に合ったグラブを使いたい
【ミズノ】硬式野球用ファーストミット(グローバルエリート・ゴールデンエイジ専用モデル)

グラブの型・皮革・芯材・紐の通し方。これまでのハタケヤマと一線を画する
【ハタケヤマ】硬式野球用グラブ/グローブ・久シリーズ:G-QY

投手のボール”質”を計測し数値化する
【SSK】テクニカルピッチ(軟式J号用)
「入荷しました!」「残り1つ!」などのSNS限定情報を配信中!
サイトには掲載しない情報やサイトの更新もお知らせいたします。
サイトには掲載しない情報やサイトの更新もお知らせいたします。
 ベースボールショップ イレブン
ベースボールショップ イレブン
北海道札幌市白石区の野球用品店「イレブン」。札幌市内で唯一のクボタスラッガー・ハタケヤマの専門店でもあり、グラブ専門メーカーのドナイヤやアイピーセレクトなど大型店や他店ではなかなか見かけない野球用品も多数お取り扱いしております。
野球用品がメインの運動店ですが「修理の専門店」でもあります。グローブやスパイクはもちろん、大きなスポーツ店ではやらないキャッチャー防具やバッグの修理、ユニフォームの加工などのメンテナンスを手がけております。
※当サイトではイレブンがおすすめする野球用品・野球情報を掲載しております。店舗にはサイトに掲載していない用品が多数あります。
野球用品がメインの運動店ですが「修理の専門店」でもあります。グローブやスパイクはもちろん、大きなスポーツ店ではやらないキャッチャー防具やバッグの修理、ユニフォームの加工などのメンテナンスを手がけております。
※当サイトではイレブンがおすすめする野球用品・野球情報を掲載しております。店舗にはサイトに掲載していない用品が多数あります。
グラブ(グローブ)
硬式用グラブ(グローブ)
軟式用グラブ(グローブ)
ピッチャー セカンド・ショート サード 外野手 キャッチャー ファースト
グラブ(グローブ)のお手入れ プロテクター グラブ(グローブ)の修理 オーダーグラブ(グローブ) グラブ(グローブ)の型付け
久保田スラッガー ミズノプロ ハタケヤマ ドナイヤ ウイルソン アイピーセレクト SSK アシックス ミズノ ゼット アンダーアーマー ローリングス バット 硬式用バット 軟式用バット
金属バット 木製バット カーボン製バット 混合バット
バッティンググローブ グリップテープ・グリップ関連グッズ トレーニングバット バット関連情報
ウイルソン ミズノ アシックス SSK ミズノプロ ディマリニ ヤナセ ゼット ルイスビルスラッガー アイピーセレクト ウィップストリップ 野球トレーニング 筋トレ サプリ 食事 野球スパイク 野球ウェア 野球用バッグ 野球コラム 野球のルール 仕事 その他スポーツ バットについて 野球関連 お役立ち用品 野球チーム 野球のプレイについて メーカー ドラフト会議 野球選手 高校野球 野球雑学 本 野球の本 食事の本 マラソンの本 仕事の本 野球用品の修理・メンテナンス 野球用品の加工・マーク・オーダー 野球ユニフォームの背ネーム・背番号加工 野球ボール キャンペーン プレゼント メーカーのキャンペーン ニュース イレブン杯 イレブン杯(野球) イレブン杯(サッカー) ショップ 飲食店 マッサージ・整体 メーカー ミズノ ミズノプロ 久保田スラッガー アンダーアーマー ドナイヤ デサント ゼット ウイルソン ヤナセ ディマリニ ニシスポーツ アイピーセレクト ハタケヤマ ニッスイ SSK アシックス WHITE BEAR(ホワイトベア) ルイスビルスラッガー 内田販売システム ナガセケンコー ウィップストリップ ローリングス フランクリン フィールドフォース UNIX(ユニックス) 泥スッキリ本舗 アクセフ ハイゴールド
ピッチャー セカンド・ショート サード 外野手 キャッチャー ファースト
グラブ(グローブ)のお手入れ プロテクター グラブ(グローブ)の修理 オーダーグラブ(グローブ) グラブ(グローブ)の型付け
久保田スラッガー ミズノプロ ハタケヤマ ドナイヤ ウイルソン アイピーセレクト SSK アシックス ミズノ ゼット アンダーアーマー ローリングス バット 硬式用バット 軟式用バット
金属バット 木製バット カーボン製バット 混合バット
バッティンググローブ グリップテープ・グリップ関連グッズ トレーニングバット バット関連情報
ウイルソン ミズノ アシックス SSK ミズノプロ ディマリニ ヤナセ ゼット ルイスビルスラッガー アイピーセレクト ウィップストリップ 野球トレーニング 筋トレ サプリ 食事 野球スパイク 野球ウェア 野球用バッグ 野球コラム 野球のルール 仕事 その他スポーツ バットについて 野球関連 お役立ち用品 野球チーム 野球のプレイについて メーカー ドラフト会議 野球選手 高校野球 野球雑学 本 野球の本 食事の本 マラソンの本 仕事の本 野球用品の修理・メンテナンス 野球用品の加工・マーク・オーダー 野球ユニフォームの背ネーム・背番号加工 野球ボール キャンペーン プレゼント メーカーのキャンペーン ニュース イレブン杯 イレブン杯(野球) イレブン杯(サッカー) ショップ 飲食店 マッサージ・整体 メーカー ミズノ ミズノプロ 久保田スラッガー アンダーアーマー ドナイヤ デサント ゼット ウイルソン ヤナセ ディマリニ ニシスポーツ アイピーセレクト ハタケヤマ ニッスイ SSK アシックス WHITE BEAR(ホワイトベア) ルイスビルスラッガー 内田販売システム ナガセケンコー ウィップストリップ ローリングス フランクリン フィールドフォース UNIX(ユニックス) 泥スッキリ本舗 アクセフ ハイゴールド